「儀式」というのがとにかく嫌いな父親のせいで、渡辺家では年中行事の類が一切行われないのだ。
日本には古来から伝わる年中行事が沢山あって、それぞれに多少の面倒くささがありながらも美しい日本の四季と連動して季節の移ろいを感じさせてくれる。
行事を通して家族の思い出や絆が積み重なる。毎年毎年一葉の写真がアルバムに追加され、その積み重ねが何時しか良くも悪くも家族の重さを演出していく。
国家というのは家族という単位の積み重ねで実は成り立っていると思っているので、つまりは年中行事が国家のそして国民性の奥深い部分を支えているのだ。
だとするならばうちの親父というのは第一級の国家反逆人といえるのかもしれない。
盆も、各種の節句も、クリスマスも鉄道の日も夏至も冬至もうなぎの日も、渡辺家では一切スルーされる。どようの丑の日に僕と兄貴が結託してどれだけうなぎが食べたいとわめいても何処吹く風で、真夏の盛りに熱々のポトフが鍋一杯に盛り付けられ、汗だくになってそれを食べさせられた記憶が幼少にある。
普段は喧嘩、というか兄による一方的な搾取と圧政が続く僕と兄がこの日ばかりは結託してうなぎを食べたい運動、うなぎムーブメントなるものをくりひろげた記憶がある。
「おかあさん、花壇にみずやるから、うなぎ、じゃなかったホースどこにある?」
「おかあちゃん、うなぎ、じゃなかったうなじがかゆいんだけれどムヒあるかな?」
このときばかりはぴったりと息の合う二人が繰り出す絶妙なうなぎコンビネーション。流石にここまで「僕たちはうなぎが食べたいんだ」と言外ににおわせると、母親も感じるものがあったらしい。
その日の夕餉は、秋刀魚を開いて照り焼きのたれで煮詰めた「さんま丼」なる物が食卓に供された。
「兄ちゃん、さんま丼うまいなあ」「ああ、弟よ」涙を呑みながらさんま丼を掻っ込む幼い兄弟の姿。それ以来さんま丼は渡辺家の食卓名物としてしばらく君臨することになる。
が、母さんの頭には僕ら兄弟はうなぎが好き、という情報がインプットされたらしく、その後上京してから一時帰省するたびにうなぎが用意されるようになるのは後の話。
どようの丑の日にうなぎがレジ横に箱積みにされるスーパー。絶対に手に届かない対象は何時しか憎しみの対象に変わるもので、その対象への愛が深ければ深いほどその憎しみは深くなる。
時代が時代だったら平積みにされK2のような山をなすうなぎのパックの中に僕はひっそりと秋刀魚の蒲焼を紛れ込ませ、その様子をツイッターで中継していたかもしれない。まあ、いまだにツイッターの使い方がいまいちよく分からんしフォロワーが殆どいないので社会を揺るがすような事にはなりはしないだろうけれど。
そんな中お正月というのは、春の花見と中秋の月を見ながら団子を食べる行為と並ぶ数少ない、必ず遵守される行事である。というか家族行事と言えばこの三つしか思い当たらない。
今年もそんなお正月がやってきた。今年のお正月は例年に無く特別なお正月になる。何せ、家族がついに一人増えるのだ。
ふだんから満願全席並みの品数がならぶ渡辺家の食卓は、この時はもっと凄いことになってしまう。
果たして加齢と共に弱体化していく僕の消化器官は、そしてまだ家族になったばかりで目の前にあるものは際限なく平らげてしまう嫁のウェストは、耐えられるのだろうか・・・
つづく

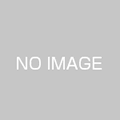
















 現役大学生の
現役大学生の










